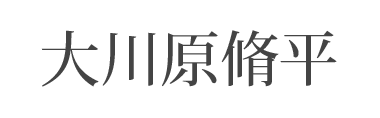少女漫画とハイジュエリー

先日、ジュエリー好きの男性と一緒にブシュロンの展示会に行ってきました。
ブシュロンといえばなのしれたハイジュエリーブランドですね。
暴力的なほどキラキラした空間にあってさえ圧倒的な輝きを放つ大量のダイヤの塊を見たりしました。超かわいいかったです。

シャンパンを片手に2人のおじさんがお姫様扱いされてキャッキャと過ごしたのですが、この空間のありよう、というか過剰な輝き、どこかに既視感があるなと思ったんです。

これだ。
少女漫画でいう光の演出効果。これ、実在していたんですね。
上のイラストも半分くらいはそうですが、実際に宝飾品の輝きの効果である場合もあります。それでも、そこを飛び越えて、ある「うつくしいもの」の演出としてのきらめきの効果は、少女漫画やそうした表現ではかなり頻繁に使われています。
この輝きが現実化したもの、あるいは現実の宝飾品の輝きがそのまま本人の輝きとして錯覚し認識されるのだとすれば、ジュエリーこそがこの「輝き」だといってもいいように思えます。
宝石の光というものは、じっさい、ふとした瞬間に目を奪うし、それは言ってしまえば装着者自身の輝きに他ならない。ジュエリーとは文字通り、つけているひとを「輝かせる」原始的で圧倒的な演出装置だったんですね。
いや、あたりまえといえばあたりまえのことをいっているのかもしれませんが、個人的にはちょっと目から鱗でした。(真珠みたいにキラキラしたやつ)
しかし、こうした輝き(そして輝きにも質があるのだなあ。、)を身にまとうことがたんにステータスであったというの、非常にわかりやすい世界ではある。
▼
さいきんではARや写真加工の技術革新によって、輝きそのものを身にまとうことも可能になりました。あたくしもそうした現象は非常に興味深く眺めています。
ただ、ブシュロンの販売員さんのアツい思いを聞くにつけ、長い歴史の文脈を「まとった」意匠を、さらに現実に身に「まとう」ことには、やはりそれなりの強さがあるものだな、といったようにも思いました。
あの「輝き」を「現実に」「手に入れる」ことができる。(数千万くらいで)
この事実がきっと、いつまでもひとを宝飾に夢中にさせているのだな、と思いました。
(雑なしめでちょっと反省しています。ジュエリーについては引き続き長い目で考えていきたいです。)